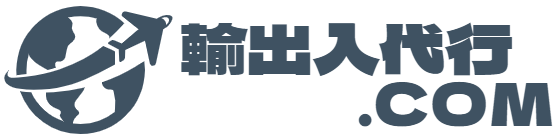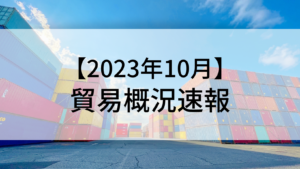消費税の輸出免税制度とは?免税対象になる範囲や仕組みを解説
国際取引が盛んになっている現在「輸出免税」について、聞いたことがあるという人もいるのではないでしょうか。
輸出免税はその名の通り、輸出時に消費税が免税となる制度のことです。
今や消費税率は10%となり(軽減税率を除く)、この10%が免税になった場合、かなり大きなコストカットになりますよね。
そこで今回は「輸出免税」をテーマに
- 輸出免税制度とは
- 輸出取引が免税となる理由
- 輸出免税の対象になる範囲
などを徹底解説していきます。
既に輸出をしている人、これからしたいと考えている人など、輸出免税について気になっている人は、ぜひ参考にしてください。
目次
輸出免税制度とは?輸出取引が免税となる理由

輸出免税制度とは、国際取引において発生する商品の輸出に伴う消費税を免除する制度です。
これは原則、消費税は「国内での商品・サービスの提供」に課税されるため、海外で消費される商品・サービスについては課税をしないという考えに基づいています。(空港出国ゲート後の免税店は国外とみなされています)
そのため、通常国内で商品が売買される際には消費税が課税されますが、輸出される商品についてはこの免税制度が適用され、消費税がかからなくなります。
この制度は、国内企業が国外市場で競争力を維持するためや、国内経済を活性化する効果もあります。
また、輸出業者にとっては、商品の価格競争力を高め、輸出市場での利益を最大化するための手段にもなります。
輸出取引の免税には二重課税を防ぐ効果もある
輸出時に消費税がかかったのち、輸入国でも販売国の消費税がかかるとなると、消費税が二重にかかってしまいますよね。
消費者側からすれば、税金に対してさらに税金がかかっているので、二重課税となり、実際の価格よりも高く感じてしまうでしょう。
輸出取引の免税には、こうした二重課税を防ぐ効果もあります。
輸出免税と切り離せない消費税について
輸出免税と消費税は、切っても切れない関係なので「消費税とは何なのか」についても簡単に説明していきます。
消費税は、商品やサービスの購入時に課される税金です。
一般的な商品やサービスに対して消費者が支払った金額の一定割合が税金として徴収されます。
日本では、2023年現在、
- 標準税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)
- 軽減税率は8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)
となっています。
消費者から徴収をしたのち、事業者がまとめて納付をする形式となっています。
消費税の納付者は課税事業者
消費税は間接税とされており、消費者が負担をしているものの、納付をしているのは商品の売買やサービスを提供している事業者です。
事業者には
- 課税事業者
- 免税事業者
の2つがありますが、そのうち「課税事業者」と呼ばれる事業者は、消費税を納付しなければなりません。
免税事業者は事業者免税点制度という制度により、消費税を納める義務を免除されています。
消費税額の計算方法

それでは、消費税がどのように計算され、納付額が決まっていくのかをみていきましょう。
消費税は「消費者より徴収した金額全てを納付しなければならない」というわけではないです。
簡単な説明となりますが、一般課税方式の場合、仕入れ時に支払いをした消費税分を控除することが可能なため、
(課税売上高×消費税率) - (課税仕入高×消費税率)=消費税納付額
となります。
例えば、年間課税売上高が2000万円、年間課税仕入高が1000万円の場合、
(2000万円×10%) - (1000万円×10%)=消費税納付額
200万円 - 100万円=100万円=消費税納付額
つまり、100万円が消費税納付額となります。
輸出のためにかかった消費税は還付の対象となる
ここまでお話をしてきた消費税ですが、最初にお話をした通り、輸出取引の場合は消費税が免税となります。
そして輸出免税取引は、輸出のために仕入れ等でかかった消費税は仕入れ税額控除をすることが可能なため、消費税還付の対象になります。
消費税還付の対象となるには
- 課税事業者であること
- 一般課税制度を適用
上記の条件を満たさなければなりません。
とはいえ、消費税率が10%となっている現在、仕入れ税額控除による消費税還付は魅力的だといえるでしょう。
ちなみに消費税還付を行いたい場合は、還付申告が必要となるので忘れないようにしてください。
輸出免税の対象になる範囲
輸出免税の対象範囲は、国税庁HPによると以下の通りとなっています。
課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。
(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
(2)国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便
(3)非居住者(注)に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け
(4)非居住者(注)に対する役務の提供
ただし、非居住者(注)に対する役務の提供であっても、国内に所在する資産に係る運送や保管あるいは国内における飲食や宿泊のほか、これらに準ずるもので当該非居住者が国内において直接便益を享受するものについては免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課されます。
(注)ここでいう 「非居住者」とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6項に規定する非居住者をいいますので、本邦内に住所又は居所を有しない自然人及び本邦内に主たる事務所を有しない法人が該当します。なお、非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上の代理権があるかどうかにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなすこととされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
輸出免税を受けるには証明が必要
輸出免税を受けるためには、ただ申告をすればいいというわけではなく、書類による証明をしなければなりません。
どのような輸出取引を行ったかにもよるものの、
- 輸出許可証
- 輸出の事実が確認できる帳簿
- 輸出取引がわかる契約書
などが必要です。
また、証明書類につきましては、7年間の保存が求められています。
輸出免税を受けたいと考えている事業者は書類の保存を欠かさないようにしましょう。
輸出免税制度を使い効率よく海外取引をしよう
ここまで「輸出免税制度」また関係の深い「消費税」について解説をしてきました。
輸出を行っている事業者にとって、こちらの制度を使うことで、より効率よく海外取引をすることができるようになります。
輸出入代行.comでは、こうした制度が活用できるような「輸出事業のサポート」など海外事業に必要なことを丸投げできるサービスを行っているので、ぜひお気軽にお問合せください。