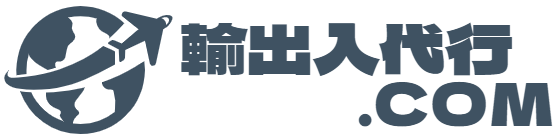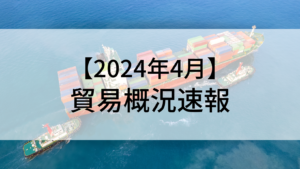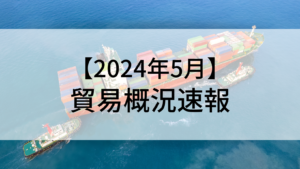バーゼル条約とは廃棄物の処理に関する条約!概要や規制対象について解説
近年、国際社会では地球環境の保護と持続可能な社会の実現に向けて、さまざまな取り組みを行っています。その中で特に重要な役割を果たしているのが「バーゼル条約」です。
これは、有害廃棄物の越境移動およびその処理の規制を目的とした国際条約で、環境保護における基盤的な取り組みとされています。
バーゼル条約は貿易取引にも密接に関わる条約ですが、意外と知られていない条約でもあります。
そこで今回は、
- バーゼル条約とは何か
- 制定の経緯や概要
- バーゼル条約の規制対象物
- バーゼル条約の将来性
などについて詳しく解説します。
国際貿易にも関わるバーゼル条約の理解を深め、国際ビジネスの観点から環境保護への理解も深めていきましょう。
バーゼル条約とは

バーゼル条約(Basel Convention)とは、有害廃棄物の越境移動およびその処分に関する規制を目的とした国際条約です。
正式には「有害廃棄物の越境移動及びその処分の規制に関する条約」といいます。(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)
バーゼル条約の主な目的としては「有害廃棄物の輸出入の規制」で、簡単に説明すると「有害廃棄物の処理コストが安かったり、規制の少ない国へ、有害廃棄物を送るのはやめましょう」という国際的な取り決めです。
バーゼル条約が制定された経緯
バーゼル条約は、1989年に採択され、1992年に発効した国際条約です。
この条約が制定された背景には、1980年代における有害廃棄物の国際的な輸送に関する問題が深く関わっています。
1980年代、多くの先進国が自国での有害廃棄物の処分コストの高さや厳しい環境規制を避けるため、これらの廃棄物を途上国や経済的に困難な国へ輸出する事例が増えました。
これらの廃棄物には、化学薬品、医療廃棄物、産業廃棄物などが含まれ、受け入れ国では適切な処分ができず、深刻な環境汚染や健康被害を引き起こしました。
そこで国連環境計画(UNEP)は有害廃棄物の越境移動に対する国際的な規制の必要性を強く感じ、1987年、国連環境計画は国際的な作業グループを設立し、条約草案の作成を開始しました。
そして1989年3月、スイスのバーゼルで開催された会議で、バーゼル条約は正式に採択されました。
条約は、各国が有害廃棄物の輸出入を管理し、適切に処理するための枠組みを示しています。
1992年5月、50カ国以上が批准し、条約が発効しました。
日本はバーゼル条約に従って輸出入を行うことが環境問題への積極的な貢献へと繋がることから、1993年に加入しました。
2023年末時点では189か国が加入しています。
バーゼル条約の概要
ここでバーゼル条約の概要を紹介します。
本条約は、前文、本文29か条、末文及び9の附属書からなり、その主たる規定は次の通り。
(1)この条約に特定する有害廃棄物及びその他の廃棄物(以下、本資料において「廃棄物」という。)の輸出には、輸入国の書面による同意を要する(第6条1~3)。
(2)締約国は、国内における廃棄物の発生を最小限に抑え、廃棄物の環境上適正な処分のため、可能な限り国内の処分施設が利用できるようにすることを確保する(第4条2(a)及び(b))。
(3)廃棄物の不法取引を犯罪性のあるものと認め、この条約に違反する行為を防止し、処罰するための措置をとる(第4条3及び4)。
(4)非締約国との廃棄物の輸出入を原則禁止とする(第4条5)。
(5)廃棄物の南極地域への輸出を禁止する(第4条6)。
(6)廃棄物の運搬及び処分は、許可された者のみが行うことができる(第4条7(a))。
(7)国境を越える廃棄物の移動には、条約の定める適切な移動書類の添付を要する(第4条7(c))。
(8)廃棄物の国境を越える移動が契約通りに完了することができない場合、輸出国は、当該廃棄物の引き取りを含む適当な措置をとる(第8条)。
(9)廃棄物の国境を越える移動が輸出者又は発生者の行為の結果として不法取引となる場合には、輸出国は、当該廃棄物の引取を含む適当な措置をとる(第9条2)。
(10)締約国は、廃棄物の処理を環境上適正な方法で行うため、主として開発途上国に対して、技術上その他の国際協力を行う(第10条)。
(11)条約の趣旨に反しない限り、非締約国との間でも、廃棄物の国境を越える移動に関する二国間または多数国間の取決めを結ぶことができる(第11条)。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/basel.html
バーゼル条約の規制対象物とは

バーゼル条約の規制対象物は、有害廃棄物とその他の廃棄物です。
これらは、特定の化学特性を持ち、適切に処理されないと環境や人間の健康に悪影響を及ぼす可能性があるものです。
具体的には経済産業省のHPに記載がありましたので、そちらを紹介します。
<原則規制対象のもの>
・バーゼル条約附属書Ⅰかつ附属書Ⅲに該当するもので、具体的には附属書Ⅷに該当するものが対象。
・バーゼル法では、バーゼル法範囲省令別表第4~6に該当するもの
鉛蓄電池(リストA1160)
廃油(A3020)
シュレッダーダスト(A3120)
医薬品(A4010)、医療廃棄物(A4020)
<原則規制対象外>
・バーゼル条約附属書Ⅸに該当するもの
・バーゼル法では、バーゼル法範囲省令別表第2または3に該当するもの
鉄くず(スチールスクラップ)(B1010)
紙くず(B3020)
繊維くず(B3030)
ゴムくず(B3040)
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/basel/outline/outline.html
バーゼル条約の規制対象物は、環境や人間の健康に有害な影響を与える可能性がある化学廃棄物、医療廃棄物、産業廃棄物、電子廃棄物などです。
経済産業省や環境省にて、バーゼル条約の規制対象物かどうかの事前確認を行っているようなので、判断がつきにくい場合はぜひ相談してみてください。
バーゼル条約の将来性
環境保護や国際協力の観点から、バーゼル条約はより重要となるでしょう。
特に将来的に重要なポイントとして、
- 電子廃棄物の増加
- 途上国支援
- 持続可能な廃棄物管理
が挙げられています。
デジタル化の進展に伴い、電子廃棄物(e-waste)が急増しています。これらの廃棄物には、有害な化学物質が含まれているため、適切な管理が必要です。
また、途上国では、有害廃棄物の適切な管理や処理技術が不足していることが多く、バーゼル条約は、技術支援やキャパシティビルディング(能力向上)を通じて、途上国が持続可能な廃棄物管理システムを構築できるよう支援しています。
そして今後は、循環経済(サーキュラーエコノミー)の考え方がより重要になるでしょう。
廃棄物を資源として再利用し、廃棄物の発生を最小限に抑える取り組みが求められています。
バーゼル条約は、持続可能な廃棄物管理の推進を通じて、こうした循環経済の実現にも貢献しています。
バーゼル条約を理解して国際社会に協力しよう
バーゼル条約は、国際社会が一丸となって環境保護に取り組む重要な枠組みです。
有害廃棄物の越境移動を適切に管理することで、地球規模の環境汚染を防ぐことを目的としています。
バーゼル条約の重要性を再認識し、私たち一人ひとりができることを考え、実行していくことが未来を守る第一歩となります。
環境問題はグローバルな課題であり、共に解決を目指す姿勢が必要なので、この記事を通じて、バーゼル条約への理解を深め、今後も環境保護の意識を高めていきましょう。
輸出入代行.comでは、輸出入事業のサポート・海外事業に必要なことを丸投げできるサービスを行っているので、ぜひお気軽にお問合せください!